- 購入・消費の促進
目次
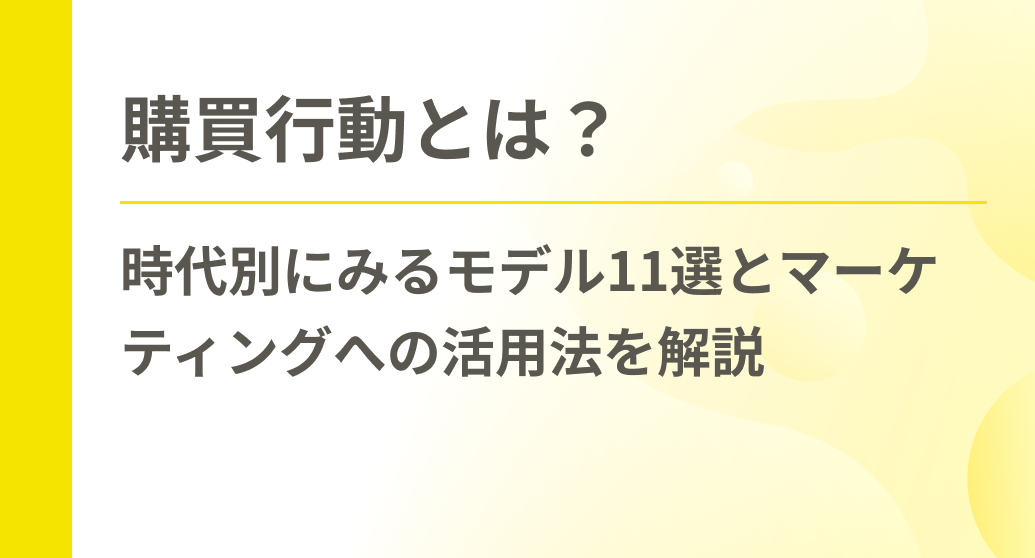
顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの流れを「購買行動」と呼びます。この購買行動を理解しておかなければ、効果的な販促・マーケティング戦略を立てるのは難しいです。
本記事では、「購買行動とは何か?」という基本から、似ているようで違う「消費者行動」との違いまでを解説。さらに、時代とともに変化してきた主要な購買行動モデルをわかりやすく紹介します。
なお、購買行動を促進させる施策を検討中なら、消費者に購入金額の全部または一部を現金で還元する販促手法「キャッシュバックキャンペーン」がおすすめです。当サイトでは、キャッシュバックの仕組みや種類、実施の流れまでをまとめた資料を無料配布していますので、下記リンクからお気軽にダウンロードしてみてください!
キャッシュバックのすべてがわかる!

顧客が「これが欲しい!」と思ってから実際に購入するまで、実はさまざまなステップがあります。ここでは「購買行動」と呼ばれるこのステップについて、わかりやすく解説していきます。
購買行動の意味やよく似た言葉「消費行動」との違い、そして時代とともに変化してきた「購買行動モデル」を見ていきましょう。
購買行動とは、一言でいうと「顧客がある商品やサービスを知ってから、実際にそれを買うまでの一連の行動や心理的な変化」です。
単にお金を支払う瞬間だけではない、ということがポイントです。その前段階で「どのような商品があるかな?」とお店やネットで調べたり、「どちらのブランドにしようかな?」と悩んだりする時間も購買行動に含まれます。
もちろん、すべての買い物で同じプロセスをたどるわけではありません。
例えば、スマートフォンやパソコンのような高価な買い物では、じっくり時間をかけて情報を集め、比較検討する人が多いでしょう。一方で、コンビニで買うお菓子のような比較的安価な商品であれば、衝動的に購入することもあります。
このように、扱う商品やサービスによって購買行動の流れやステップの数は変わっていくのです。
購買行動とよく似た言葉に「消費者行動」というものがあります。これは購買行動と少し意味が違うので、ここで整理しておきましょう。
消費者行動とは
商品やサービスを買う前の情報収集から、実際に購入し、それを使用した後の評価、さらには最終的にそれをどうするか(例:使い続ける、捨てる、リサイクルする、人に譲るなど)まで、「消費」に関わるすべての行動や心理状態を指す。
簡単に言うと、「購買行動」が主に「買う」という行為とその前後のプロセスに焦点を当てているのに対し、「消費者行動」はより広い範囲の行動を含んでいます。
イメージとしては、「消費者行動」という大きな円の中に「購買行動」が含まれている、と考えるとわかりやすいでしょう。例えば、環境のことを考えて使い終わったペットボトルをリサイクルするのも消費者行動のひとつです。
購買行動モデルとは、多くの人に共通して見られる購買行動のプロセスを、わかりやすく段階的に示した「型」や「地図」のようなものです。企業などがマーケティング活動を考える際に、顧客を理解するための基本的な枠組みとして活用されています。
この購買行動モデルはひとつだけではなく、時代背景や情報技術の進化に合わせて、さまざまな種類が考え出されてきました。
昔はテレビや新聞がおもな情報源でしたが、やがてインターネットが登場。今ではSNSが欠かせないツールになりました。こうした時代の変化に合わせて、人々の買い物の仕方も変わり、それを反映した新しい購買行動モデルが登場してきたのです。
本記事では、後の章でこれらの購買行動モデルを「マスメディア時代」「Web(インターネット)時代」「SNS時代」という時代区分に分けて、具体的に紹介します。

顧客の購買行動を知るためには、購買行動モデルを理解しておく必要があります。その理由は大きく分けて次の4つです。
ひとつずつ見ていきましょう。
購買行動モデルは顧客のインサイト(深層心理)を探り、行動を読み解くための強力なツールです。
顧客は気まぐれに行動しているように見えても、ある程度共通した心理プロセスや行動パターンを持っています。購買行動モデルは、このような典型的なパターンを「認知」「興味」「検索」「比較」といった段階に分けて示してくれるのです。
例えば「AISASモデル」を知っていれば、「最近の顧客は興味を持ったらまず検索(Search)するんだな」と理解できます。この理解があれば、「検索されたときに備えて、自社サイトに詳しい情報を載せておこう」といった顧客の行動に基づいたアクションを考えることができます。
「今、ターゲット顧客はどの段階にいるのか?」を意識し、その段階に最適なメッセージやチャネル(伝える手段)を選択するには、購買行動モデルの活用が効果的です。
顧客は、購買プロセスの段階によって求めている情報や、心に響くメッセージが異なります。
例えば、まだ商品を知らない「認知」段階の顧客に対して、いきなり購入を強く勧めても効果は薄いでしょう。まずは興味を持ってもらうための魅力的な広告や話題づくりが必要です。一方、複数の商品を比較している「比較検討」段階の顧客には、商品の特徴や優位性、他社製品との違いなどを明確に伝えなければなりません。
モデルに基づいて戦略を設計し、適切なタイミングで、適切な情報を、適切な方法で顧客に届けていきましょう。
購買行動モデルは、自社のマーケティング活動における課題を発見し、改善策を考えるための「診断ツール」としても機能します。
例えば、自社商品が「広告での認知度は高いし、Webサイトへのアクセスも多いけれど、なかなか購入につながらない」という状況があったとします。
この状況をAISASモデルに照らし合わせると、「検索」から「行動」の間のプロセス、あるいは「行動」そのものの段階に何か問題があるのではないかと推測できます。「比較検討段階で他社製品に負けているのか?」「購入手続きが複雑すぎるのか?」といった仮説を立て、原因を探るきっかけになるのです。
目まぐるしく変化する時代や市場環境、テクノロジーの変化に対応するには、さまざまな購買行動モデルを理解する必要があります。
かつてマスメディアが中心の時代には「AIDMAモデル」が有効でした。しかし、インターネットの普及で「AISASモデル」が注目され、SNSが生活に浸透した現代では「ULSSAS」や「RsEsPs」といった新しいモデルが登場しています。
古いモデルしか知らないと、「なぜテレビCMに反応しないのか」「SNSでの口コミがなぜこれほど影響力を持つのか」といった変化の本質を理解できず、効果のない施策を実施してしまうおそれがあります。
最新の購買行動モデルを取り入れて、時代遅れにならないマーケティング活動を実施していきましょう。

ここでは、マーケティングの実践で役立つ代表的な購買行動モデルを次の3つの時代別に紹介します。
多様な消費者へアプローチをするためにも、それぞれの時代背景を理解していきましょう。
まずはテレビやラジオ、新聞、雑誌といった「マスメディア」が情報発信の中心的な役割を担っていた時代の購買行動モデルです。
この時代は、企業から私たち消費者へ、情報が一方向的に流れるのが特徴でした。インターネットが登場する前の購買行動モデルですが、人が物を買うときの基本的な心理プロセスを示しています。
ここでは、代表的な3つのモデルを見てみましょう。
| 購買行動モデル | 構成要素とその意味 |
|---|---|
| AIDA(アイダ) | Attention(注意):広告や店頭で「なんだろう?」と商品やサービスに気付く Interest(関心):「おもしろそう」と興味を持つ Desire(欲求):「これが欲しい」という気持ちが高まる Action(行動):実際に購入の行動をとる |
| AIDMA(アイドマ) | Attention(注意):広告や店頭で「なんだろう?」と商品やサービスに気付く Interest(関心):「おもしろそう」と興味を持つ Desire(欲求):「これが欲しい」という気持ちが高まる Memory(記憶):「欲しい」と思ってもすぐ買わず、「覚えておく」 Action(行動):後日思い出して購入する |
| AIDCAS(アイドカス) | Attention(注意):広告や店頭で「なんだろう?」と商品やサービスに気付く Interest(関心):「おもしろそう」と興味を持つ Desire(欲求):「これが欲しい」という気持ちが高まる Conviction(確信):「本当にこれでいい」と確信する Action(行動):購入する Satisfaction(満足):購入後に「満足」する |
AIDMA(アイドマ)は、基本的な購買心理の流れであるAIDAに「Memory(記憶)」が加わっているのが最大の特徴です。
例えば、夜にテレビCMで見たお菓子のことを「おいしそう、今度買ってみよう」と覚えておき(Memory)、数日後にスーパーマーケットの店頭でその商品を見つけて「あ、これCMでやってたやつだ!」と思い出して購入する(Action)。
このように認知から購買までに時間差があるケースを説明するために、「Memory(記憶)」のステップが組み込まれたのです。
次に、私たちの生活にインターネットが急速に普及し始めた時代の購買行動モデルを見ていきます。
この時代になると、消費者はテレビや雑誌の情報をただ受け取るだけではありません。自らパソコンや携帯電話を使って能動的に情報を「検索」したり、さまざまな商品を「比較検討」したりすることが当たり前になってきました。
企業サイトはもちろん、口コミサイトや個人ブログなども重要な情報源となり、購買プロセスはより複雑化します。ここでは代表的な4つのモデルを見ていきましょう。
| 購買行動モデル | 構成要素とその意味 |
|---|---|
| AISAS(アイサス) | Attention(注意):商品・サービスを認知する Interest(関心):興味を持つ Search(検索):能動的に情報を検索する Action(行動):購入する Share(共有):購入後に情報を共有・発信する |
| AISCEAS(アイシーズ) | Attention(注意):商品・サービスを認知する Interest(関心):興味を持つ Search(検索):能動的に情報を検索する Comparison(比較):複数の商品を比較する Examination(検討):購入するかどうか検討する Action(行動):購入する Share(共有):購入後に情報を共有・発信する |
| DECAX(デキャックス) | Discovery(発見):コンテンツを通じて企業や商品を発見する Engage(関係構築):コンテンツを通じて関係を深める Check(確認):購入前に口コミなどを確認する Action(行動):購入する eXperience(体験と共有):購入後の体験を共有する |
| MOT(モット) | ZMOT(Zero Moment of Truth):店舗訪問や購入「前」のオンラインでの情報収集の瞬間 FMOT(First Moment of Truth):店頭で商品を見て購入を決める最初の数秒間 SMOT(Second Moment of Truth):購入後に商品を「使用」する体験の瞬間 TMOT(Third Moment of Truth):使用後の感想を共有・発信する瞬間 |
AIDMAの「Memory(記憶)」に代わり、「Search(検索)」と「Share(共有)」を入れたのがAISAS(アイサス)です。
「Share(共有)」された情報が、別の消費者の「Attention(注意)」を引きつけ、「Search(検索)」の対象になっていく。こうすることで、新たな購買行動のループが生まれるのです。
企業は、消費者が良い「Share(共有)」をしたくなるような商品・サービス体験を提供することが、より一層重要になったことを示しています。
この「Share(共有)」を後押しする施策には、さまざまなものが考えられます。その中でもおすすめなのが、株式会社スコープが提供する「ウォレッチョ」を活用したキャッシュバックキャンペーンです。

「ウォレッチョ」なら、ATMからの受取り・銀行振込・電子マネー残高チャージなど5種類の送金方法に対応しており、顧客が自分に合った方法でキャッシュバックを受け取れます。
「ウォレッチョ」について詳しく知りたい方は、下記リンクからサービス資料をダウンロードしてご覧ください!
売上アップ施策との相性も抜群!
最後に、SNS時代の購買行動モデルを見ていきましょう。
この時代の大きな特徴は、友人や知人、あるいはフォローしているインフルエンサーの投稿に対する「共感」が購買のきっかけになる点です。また、情報が「いいね!」やシェアを通じてあっという間に「拡散」されていきます。
企業からの公式情報よりも、一般ユーザーが発信するリアルな情報(UGC:ユーザー生成コンテンツ)の影響力が増している点も見逃せません。ここでは代表的な4つのモデルを紹介します。
| 購買行動モデル | 構成要素とその意味 |
|---|---|
| VISAS(ヴィサス) | Viral(口コミ):SNSなどで情報が口コミで広がる Influence(影響):投稿を見て影響を受ける Sympathy(共感):「良いね」と共感する Action(行動):購入などの行動を起こす Share(共有):自身の体験を共有する |
| SIPS(シップス) | Sympathize(共感):投稿に共感する Identify(確認):自分事として情報を確認・理解する Participate(参加):いいね、シェア、購入などで参加する Share & Spread(共有・拡散):参加した体験や情報を共有・拡散する |
| ULSSAS(ウルサス) | UGC(ユーザー投稿):SNSで一般ユーザーの投稿を見る Like(いいね):投稿に「いいね」する SNS Search(SNS検索):ハッシュタグなどでSNS内検索する Search(Web検索):GoogleなどでWeb検索する Action(購買):購入する Spread(拡散):自身の体験をSNSなどで拡散する ※UGCはUser Generated Contentsの略 |
| RsEsPs(レップス) | Recognition(認識):製品・サービスを認識 search/share/spread(検索・共有・拡散):認識後に検索・共有・拡散 Experience(体験):無料体験やイベント参加など search/share/spread(検索・共有・拡散):体験後に検索・共有・拡散 Purchase(購買):製品・サービスを購買 search/share/spread(検索・共有・拡散):購買後に検索・共有・拡散 |
比較的新しい購買行動モデルとして注目されているのが、RsEsPs(レップス)です。このモデルのユニークな点は、「search/share/spread(検索・共有・拡散)」のプロセスが、商品を認識した後、体験した後、そして購買した後と、合計3回も登場することです。
消費者がひとつの段階で完結せず、常に情報を探し(Search)、他者と共有し(Share)、さらにその情報を広めながら(Spread)、慎重に意思決定を進めている様子を表しています。
このように、SNS時代の購買行動モデルはユーザー同士のつながりや情報発信を大切にしています。SNSを活用した効果的な宣伝方法について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひご覧ください!

前章で購買行動モデルを紹介しましたが、モデルは知っているだけでは意味がありません。実践に活かしてこそ価値があります。
そこでこの章では、紹介した購買行動モデルを具体的なマーケティング戦略に落とし込み、成果につなげるための5つのステップを解説します。
購買モデルを理解し、効果的な施策を実施していきたい方は、ぜひ本ステップに沿って進めてみてください。
最初のステップは、数ある購買行動モデルの中から自社の状況に最も合ったものを選定することです。
例えば、高価で専門的なBtoB(企業向け)商材と、SNSでの流行が重要な若者向けファッションアイテムでは顧客の購買行動はまったく異なります。前者であれば比較検討を重視したAISCEASやコンテンツ起点のDECAXを参考にします。一方、後者であればSNSでの拡散を含むULSSASやRsEsPsのほうが適切です。
必要に応じて複数のモデルを組み合わせたり、自社に合わせてカスタマイズしたりする柔軟性も大切です。
次のステップは、カスタマージャーニーマップの作成です。
カスタマージャーニーマップとは
顧客が、商品やサービスを認知してから購入し、さらにその後の関係に至るまでの「旅(ジャーニー)」を、行動・思考・感情などの観点から時系列で可視化したもの。
顧客の視点に立って購買プロセス全体を具体的に描き出すことで、各段階(例:「認知」「興味」「検索」「比較検討」「購買」「共有」など)における顧客の体験やニーズを深掘りしていきます。
例えば「比較検討」段階であれば、
といった具体的な顧客像が想像できます。
このように顧客の「旅」を詳細に描くことで、次のステップであるKPI設定や施策立案の精度を高めることができるのです。
次のステップは、各段階におけるマーケティング活動の目標値「KPI」を設定します。
KPI(重要業績評価指標)とは
最終的な目標(KGI:重要目標達成指標、例:売上高など)を達成するために、プロセスごとに達成度合いを測るための中間的な指標のこと。
KPIを設定することで、マーケティング施策が「なんとなく」実施されるのを防ぎ、その成果を客観的に測定できるようになるのです。
例えば、次のようなKPIが考えられます。
| 段階 | KPIの例 |
|---|---|
| 認知 | Webサイトの新規訪問者数 SNSアカウントのインプレッション数(表示回数) ブランド名の検索回数 |
| 比較検討 | 商品比較ページの閲覧数 資料ダウンロード数 問い合わせ件数 |
| 購買 | 購入数 購入単価 購入率(コンバージョンレート) |
より実用的なKPIを設定したい方は、SMARTの法則(具体的か、測定可能か、達成可能か、関連性があるか、期限があるか)を意識してみてください。
設定したカスタマージャーニーマップとKPIをもとに、具体的な施策を計画していきましょう。
具体的な計画例
例えば、「認知段階のKPI」でWebサイトの新規訪問者数を増やしたい場合で考えると、次のような施策が考えられます。
ただし、利用できるリソース(人員、予算、時間)も有限です。優先順位をつけて、着実に実行可能なものから計画を立てましょう。
マーケティング施策は実施して終わりではありません。設定したKPIに対してどのような効果をもたらしたかを定期的に測定・分析し、その結果に基づいて改善を続けていきます。
具体的な効果測定の例を見ていきましょう。
例えば、Google Analytics(Webサイトの分析ツール)のデータから、「どの段階で顧客が離脱しやすいか?」を客観的に把握します。この分析結果に基づき、「効果が見られなかった施策の原因を分析し、内容を見直すか、場合によっては中止する」といった改善策を検討していくのです。
この「計画(Plan)→実行(Do)→測定・評価(Check)→改善(Action)」というPDCAサイクルを継続的に回していくことが、マーケティングの成果向上につながります。

目まぐるしく変わる顧客の心理や行動パターンに適切に対応していくには、さまざまな顧客購買モデルを理解しなければなりません。
本記事で得た知識をヒントに、まずは自社の商品やターゲット顧客に最も近いモデルを選んでみてください。そして、紹介した実践ステップを参考にして具体的な施策を計画し、小さな一歩でも良いので試してみましょう。
試行錯誤を重ねることで、きっと顧客とより良い関係を築き、ビジネスを成長させる道筋が見えてくるはずです。
下記の記事では、顧客が商品やサービスを知ってから購入に至るまでの心の流れ「購買心理」について詳しく解説しています。気になる方はこちらの記事もご覧ください!
草刈直弘
株式会社スコープ ウォレッチョ事業責任者。スコープ入社後、大手流通・外資系日用品メーカーなどの販促支援に従事。大手アパレル×衣料用洗剤ブランドタイアップ、家電ブランド店頭販売員教育プログラムのデジタル化などの新規案件を数多く担当。キャッシュバック販促のDXから着想を得て、2021年にウォレッチョ事業を立ち上げ~現職。
